
「知ることにより変わる・変えられる」を理念に国内外の良質な映画を毎⽉お届け
MOVIE- 知ることにより変わる・変えられる-
「知ることにより変わる・変えられる」を理念に国内外の良質な映画を毎⽉お届け

Episode.13
娘を誘拐された普通の母親が犯罪組織と対決した……メキシコで起きた実話『母の聖戦』
テオドラ・アナ・ミハイ監督インタビュー
SNS、未曾有の⻑寿社会、家⽗⻑制や終⾝雇⽤制度の崩壊、多様なジェンダー・アイデンティティやセクシュアリティの可視化、顕著になったリプロダクティブ・ヘルス/ライツの貧困、そして、新型コロナウィルス……現代は前例のないことだらけ、ロールモデル不在の時代です。だからこそ、私達は⾃分のいる社会や世界をもっとよく知ることで、新しい⽣き⽅をデザインしていけるのではないでしょうか。「知ることにより変わる・変えられる」を理念に国内外の良質な 映画を毎⽉お届けしていきたいと思います。
年間約6万件(推定)の誘拐事件が発生するメキシコ。麻薬カルテルを含めた様々な犯罪組織が営利目的に一般の市民を誘拐している。だが、メキシコ当局は市民を助けようとしない上に、犯罪組織の人間もまた市民に紛れ込んでいるので被害者家族は誘拐犯の言いなりになるしかないという。
この恐るべきメキシコの現状を描いた社会派映画『母の聖戦』が1月20日に公開される。メキシコで3年間娘を探し続けた後、反誘拐ビジネスの活動家になった実在の女性ミリアム・ロドリゲス・マルティネスを主人公に描いた作品だ。(映画はミリアムさん以外の当事者の体験も交えたフィクションなので、ミリアムさんは”シエロ”と設定されている)
本作が非常に興味深いのは、”普通の母親”が犯罪組織を追い詰めていく緊迫したスリリングな展開に加え、被害者だった彼女が暴力に取り込まれていくさまである。プロデューサーに現代ヨーロッパ映画界を代表する名匠ダルデンヌ兄弟をはじめ、『4ヶ月、3週と2日』のクリスティアン・ムンジウ、そして『或る終焉』『ニュー・オーダー』で知られるメキシコの俊英ミシェル・フランコらが名を連ねた本作は、ワールドプレミアとなった第74回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で勇気賞を受賞し、第34回東京国際映画祭では審査委員特別賞を受賞した。
本作で劇映画デビューしたテオドラ・アナ・ミハイ監督に制作の背景について話を聞いた。

■『母の聖戦』STORY
メキシコ北部の町で暮らすシングルマザー、シエロのひとり娘である十代の少女ラウラが犯罪組織に誘拐された。冷酷な脅迫者の要求に従い、20万ペソの身代金を支払っても、ラウラは帰ってこない。警察に相談しても相手にしてもらえないシエロは、自力で娘を取り戻すことを胸に誓い、犯罪組織の調査に乗り出す。そのさなか、軍のパトロール部隊を率いるラマルケ中尉と協力関係を結び、組織に関する情報を提供したシエロは、誘拐ビジネスの闇の血生臭い実態を目の当たりにしていく。人生観が一変するほどのおぞましい経験に打ち震えながらも、行方知れずの最愛の娘を捜し続け るシエロは、いかなる真実をたぐり寄せるのか……。
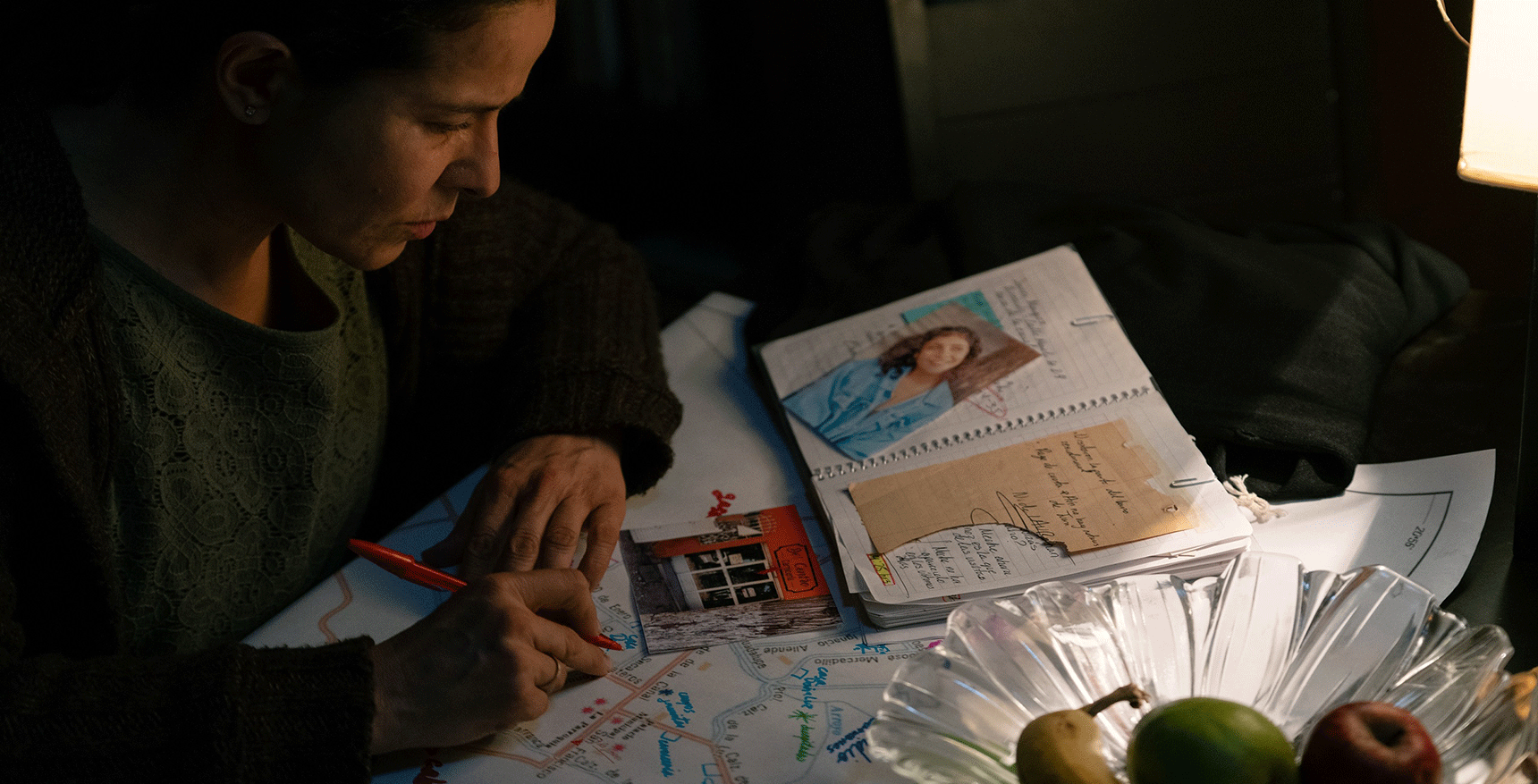
■「母の日」に犯罪組織に暗殺された実在の母
ーーなぜ、この映画を撮ろうと思ったのですか?
テオドラ・アナ・ミハイ監督(以下、ミハイ監督):シエロのモデルとなったミリアム・ロドリゲス・マルティネスに2015年に会いました。普通の50代の優しそうなお母さんに見えるのに、彼女が自分の体験を語る言葉に暴力が満ちていることに驚いたんです。彼女は銃を身につけていて「毎朝起きるたびに、この拳銃で自殺するか、人を撃ちたいと思う」と話していました。これほど優し気な普通の女性になぜこのような暴力性が生まれたのか。それを理解したいと思い、映画化を切望しました。

ミハイ監督:いいえ。当時彼女はそこまで有名でなく、私が外国人だったから心を開いてくれました。ローカルのジャーナリストを信用できなかったのかもしれません。とにかく、彼女はメキシコの現状が国際的に知られることを望んでいました。

■犯罪組織がほかの組織や個人に外注し、本当の犯人が分からない
ーー犯罪組織がほかの組織や個人に誘拐を外注するなど、非常に複雑で本当の犯人が誰か分からないというメキシコの現状に驚きました。メキシコでは年間6万件も誘拐事件が起こっているようですが、なぜ警察は誘拐の背後に麻薬カルテルなどの犯罪組織が複数あることを知りながら、何もしないのでしょうか?
ミハイ監督:シエロだけでなく誘拐の被害者たちにも取材して色々な証言を聞きましたが、メキシコの警察、軍隊や司法は力がなく麻痺した状態。警察、軍隊と司法も対立していたり、当局のなかに賄賂が横行していたり、犯罪組織と密接につながっている市民もいたり、単純に人員不足であったり……実に様々な要因が絡んでいるようです。
ーー実際の誘拐の被害者家族はミリアムさんのように自分で調査を進めるのですか?
ミハイ監督:はい。本当に、実在のミリアムに起こったようなことが起きているんですよ。ミリアムは事件後、誘拐ビジネスに抵抗する活動家として有名になったがゆえに、シンボリックな”母の日”を選んで殺されてしまいました。市民を守るべき当局がまったく機能しないと、シエロのように自分で問題を解決するしかない。あるいは、解決しようと試みるしかない。でもそれは、それだけ自分の身を危険にさらすことなんです。
肉体的な暴力だけでなく、”暴力の連鎖”に自分を委ねてしまい、自分自身のなかにも暴力が生まれてしまうことにもなります。だからこそ、脚本を書く段階から気をつけたのは、登場人物を”善悪”で描かないこと。シエロは目的のために暴力を辞さなくなっていき、彼女の行動はどんどんグレーになっていく。でも私たちは人間を単純な善悪でジャッジできるでしょうか?
ーー愛が暴力を招くという矛盾が印象的でした。
ミハイ監督:この物語は私が数々の証言を得て映し出したダークな現実。悲観的な社会ですが、同時に、ミリアムの力強さ、そして、レジリエンス(困難で脅威を与える状況にもかかわらず、うまく適応する過程や能力。精神的回復力)も映し出したかった。ミリアムはそういう能力をもった女性だということを伝えたかったんですよね。

■チャウシェスク政権を逃れたテオドラ・アナ・ミハイ監督の生い立ち
ーー監督は7歳のときに、ニコラエ・チャウシェスク政権を逃れてご両親がベルギーに移住されたと聞きました。しかし、子供だった監督はご両親の人質としてルーマニア政府により国内にしばらく止め置かれていたとか。そういった監督の生い立ちを知ると、この原題『La Civil(市民)』が非常に意味深に思えます。
ミハイ監督:このタイトルはメタファーです。中米、特にメキシコで多発している行方不明事件に関して、一般”市民”が自分で解決をしなくてはいけないことを示唆しています。そして、私の生い立ちも、この映画を作るという動機にどこかで影響しているでしょう。当時のルーマニア当局は市民の味方になり得なかったですし、親戚や友人のなかにも秘密警察が紛れ込んでいて誰も信用することができませんでした。異なる派閥のカルテルが市民に紛れ込んでいるというメキシコと、当時のルーマニアは似ています。実際にメキシコで取材中も、私はどこか”既視感”を覚えていたんですよね。やはり、私の個人的な経験もこの映画に大きく影響していると思います。
ーーラストシーンはあえて余白を残していますよね。なぜでしょう?
ミハイ監督:ラストは観客の皆さんの解釈に任せたいと思いますが、私がリサーチするなかで”殺された”はずの人がお葬式も終わった後にひょっこりと帰って来たケースもありました。警察が遺骨のDNA検査をしたと被害者家族に嘘を言ったんです。
ーーこの映画が社会にどのような影響を与えると思いますか?
ミハイ監督:私は政治家でも活動家でもなく、映画作家です。社会に何か変化を与える、あるいは、社会にとって大事なテーマを語ることを通して問題提起していきたい。小さくても映画を通して問題提起をするのが、私のできる社会貢献だと思うし、私の映画をきっかけに議論の場が生まれてほしい。その結果、変化が起こればいいなと思っています。
2023.1.19 UP

- Waka Konohana
- 映画ジャーナリスト、セクシュアリティ・ジャーナリスト。⼿がけた取材にライアン・ゴズリング、ヒュー・ ジャックマン、ギレルモ・デル・トロ監督、アン・リー監督など多数。
セックス・ポジティブな社会を⽬指す「セクポジ・マガジン」ニュースレターを配信中。 - newsletter instagram twitter Facebook









